| 花咲く夜 2
〜written
by 真砂〜
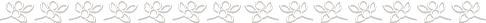
「――さて。詳しい話を聞かせてもらおうか」
真澄がマヤを振り返ると、彼女は気まずそうに自分の足元に視線を落とした。
その頼りない様は、元々小さな身体がさらに一回り小さく見えるほどだ。
真澄はマヤの顎に手をかけて彼女を上向かせる。
「君を怒らせるようなことをしてしまったか?」
「ううん…。違うよ……」
「じゃあどうして」
「……速水さんの口から最後の言葉を聞くのが怖かったから、聞きたくなかったから……」
「……………」
「だから、あたし、逃げだしちゃったの……」
「………なんだって?」
真澄が怪訝そうに眉をひそめると、マヤは再びうなだれた。
「本当はね、最後くらいはかっこよく、大人の女性として振舞おうと思ってたの。
静かに最後の言葉を受け入れて、笑ってさようならって言うつもりだったの。
でも結果はこの通り、最後の最後まで速水さんに心配をかけただけだった。速水さんに釣り合うように大人っぽい服を着て、お化粧も
きちんとして行ったのに中身はやっぱり変わらないのよね。これじゃあ、速水さんがいつまでたってもあたしを子供としか見てくれないのも
当然だと思う」
「………………」
マヤは鼻をすすり、こみ上げる涙を堪えようと必死だった。
「ひとつ訊きたいんだが……」
かたや真澄は、何とも言えぬ情けない表情でマヤを見下ろした。
「やたらと『最後』を連発しているが、それは何なんだ? まさか…とは思うが、君は今夜、俺が別れ話をするとでも思っていたのか?」
「だって、そうなんでしょう?」
マヤに即答されて、真澄は一瞬押し黙り、その後、浅くため息をついた。
「何故そう思ったのか、理由を聞かせてくれないか?」
「速水さんから大事な話があるって言われたときの電話、すごく深刻そうだったわ。レストランでも、速水さんはずっと難しそうな顔をして、
何か言おうとして、でもなかなか言い出せないって様子だったもの。……それに……」
マヤが表情を曇らせて、口篭もった。
「それに、なんだ?」
「……………」
「いいからはっきり言いなさい。言ってくれないと、何も伝わらない」
「……………」
「マヤ」
少し苛立ちを含んだ声に促され、マヤは諦めたように肩を落とした。
「速水さんは、あたしのこと、女として愛してないもの……」
マヤがそう呟くと、すうっ、と真澄の眉間に深い皺が刻まれ、その整った顔から一切の表情が失われた。
だが、その眼光だけが暗い光を放ち、マヤをたじろがせる。
「……俺が君を女として愛してない、だと? それは、聞き捨てならないな」
怒声を浴びせるでもなく抑揚のないその声音が、かえって真澄の凄みを増している。
マヤには、真澄が本気で怒っているのが肌で分かった。
今まで、マヤが、これほど真澄を怖いと思ったことはない。
だが、マヤは拳を握り締め、真澄を正面から見据えた。真澄の迫力に呑まれてしまわないように、ありったけの勇気を振り絞って。
「だって、速水さんは、いつまでたっても、あたしに触れようとはしなかった」
真澄を責めるふうでもなく、いっそ穏やかといえる口調で放たれた言葉に、真澄は大きく目を瞠った。
マヤは大きく息を吐き、これが真澄と向き合える最後の機会かもしれないなら、わだかまりの残らぬように、自分の気持ちを
全て晒してしまおう、と、そう心を決めたのだ。
「あたしだって、恋人同士が何をするのかくらい分かってる。あたしは男の人とそういうお付き合いをしたことがないから、最初は
深く考えなかったけど、一年近くも付き合っていながら何もないなんて、やっぱり不自然なことでしょう? それは、速水さんがあたしの
ことを子供としか見れないから……。あたしに…、その…、なんていうか、『女』を感じないからなんでしょう……?」
この手の話題を赤裸々に語るのが恥ずかしくて、マヤは頬を赤らめて俯いてしまう。
マヤと真澄は、触れ合うだけの口付けなら、何度か交わした。
だが、それ以上のことを、真澄は決して求めようとはしなかった。
夜、マヤと出かけても、日付が変わる前に必ず彼女をマンションに送り届け、お茶の一杯も飲むことなく、自宅へ戻っていく。
マヤに触れることなく、真澄は常に紳士的に振舞うのだ。
交際が始まってしばらくの間は、マヤは何の疑問も抱かずに、その関係に満足していた。
むしろ、奥手なマヤにとっては、二人の関係が急速に進んでいくことには抵抗があったのだ。
だが、半年が過ぎ、十ヶ月が過ぎ、もうすぐ一年になろうとすれば、さすがのマヤも不安を隠せなくなってくる。
身体を繋ぐことは、愛し合う二人にとっては、ごく自然な成り行きだという。
大人の真澄がそれをマヤに求めないということは、彼がマヤを大人の女性として見ていないのだという事実を突きつけられているようで、
マヤを激しく落ち込ませた。
内実ともに子供っぽい自覚があっても、マヤはもう、れっきとした成人女性なのだから。
「速水さんがあたしのことを大切にしてくれてるのはよく分かってるの。
でも、それは、紫のバラの人が、長年見守り続けた女優であるあたしのことを特別扱いしてくれてるだけじゃないかって考えたら、
当を得ているような気がして、すごく不安になった。あなたは優しい人だから、女としてのあたしに興味を無くしてしまったとしても、
情の移ったあたしを放っておけないだけなんじゃないか、とか、家族愛に似た思いであたしと付き合っているんじゃないか、とか、
考え出すとキリがなかったの……」
マヤの切々たる告白にも、真澄は表情を凍りつかせたまま、口を挟む気配は見られない。
「だから、覚悟してたの。名ばかりの恋人の関係が終わるときを……」
二人の間に沈黙が流れていく。
重く長い沈黙だった。
そして、それを破ったのは、真澄の深い深いため息だった。
「馬鹿だ馬鹿だと思っていたが、まさかここまでだったとは……」
真澄が心底呆れたというように吐き捨てた。
思わず唇を噛み締めたマヤに、真澄は苦々しく笑いながら、小さく首を横に振った。
「俺のことだよ」
「え……?」
「俺の態度が君をそこまで不安にさせていたなんて、夢にも思わなかった。どうやら俺は、いつまでたっても女心の分からない
朴念仁らしい。だけど、やっぱり君も馬鹿だな。まさか君に気持ちを疑われていたなんて、さすがにショックだったぞ。
俺にとっての女は、君以外にいるわけがないのに」
「嘘…、そんなの嘘よ!」
「嘘じゃないさ。それに、俺が君の身体を欲しがってないなんて思われるのも心外だ。ずっと焦がれ続けた君がそばにいて、
触れたいと思わないわけがないだろう?君には分かってもらえないだろうが、それを耐え忍ぶのは、並大抵のことじゃないんだぞ」
真澄とマヤはれっきとした恋人同士であって、マヤが真澄を拒むような素振りを見せたこともないはずだった。
それなのに、どうして真澄がマヤに触れることを禁じなければならないというのか。
マヤがいくら考えても、答えは見当たらない。
真澄はマヤを傷つけたくないから、適当なことを言っているのではないか。
そんな思いがありありと分かる眼差しで、マヤは真澄を見据えた。
「もし、ひとたび君の身体を開いてしまったら、俺はきっと会うたびに君を求めてしまうだろう。
だが、限られた時間の中で、人目を気にして密会し、身体を重ね続けるなんて、まるで三流の不倫ドラマだ。
やましい関係でもないのに、そんな安っぽい真似を君にさせたくはなかった。だから、君との関係を隠している間は、
君の身体には向き合わないと決めたんだ」
「……そんなことで、あたしに触れなかったの……?」
呆気にとられたマヤに、真澄が複雑な笑顔を返した。
「『そんなこと』じゃないぞ。俺はともかくとして、君は会える時間をベッドで過ごすよりも、まずは、人目を憚らずに二人で街中を歩いたり、
映画を見に行ったり、買い物をしたり、そんな付き合い方を望んでいるんじゃないのか?」
マヤは返す言葉が浮かんでこなかった。
たしかに、真澄の言うとおりだったからだ。
恋愛経験の乏しいマヤには、身体の関係よりも、真澄の言うように、ごく普通の恋人同士がするような、たわいもない、爽やかな
付き合い方に憧れを抱いていた。今のような秘密の関係を続けている状況だと、なおさらにそう思う。
真澄は、そんなマヤの思いを汲み取っていたのだ。
真澄はどんなときも、自分を抑えてでも、マヤを優先させる。
振り返ってみれば、昔からずっとそうだったはずだ。
それなのに、マヤは一方的に勘違いをして、真澄の気持ちを疑い、彼を振り回してしまった。
真澄の気持ちが嬉しくて、そして自分が情けなくて、マヤの瞳に涙が滲む。
それを、愛しげに、真澄が拭った。
「そもそも、後ろ暗いところなど何もないのに、こんな付き合い方を押し付けてしまって、君に対して後ろめたい気持ちがあった。
だけど、物分りの良すぎる君に、すっかり甘えてしまっていたんだ。……本当にすまなかったな」
「謝らないで。謝らなきゃいけないのは、あたしのほうなんだから……。ごめんなさい。あたし、鈍感で馬鹿だから、速水さんの気持ちに
気付かなくて……本当にごめんなさい……」
真澄はマヤの頭を胸に押し付けるようにして、彼女を優しく抱きしめた。
「鈍感で馬鹿なのは、お互い様だ。今夜、君がいつになくめかしこんでたから、もしかしたら俺の目的を見抜かれていたのかと
思っていたんだが、まさかそれが最後の晩餐のためだったとはな。とんでもない見込み違いだったよ」
「……目的?」
さも可笑しいと言いたげな真澄に、マヤが不思議そうに首を傾げた。
「まだ分からないのか?」
「だから、何が?」
「じゃあ種明かしをするから、目を瞑って、手を出して」
「え?」
「いいから。俺がいいと言うまでは、絶対に目を開けるなよ」
なにやらよく分からないものの、マヤは素直に目を閉じて、真っ直ぐ両腕を突き出した。
それはさながら、ドラマなどでよく見かける、自首してきた犯罪者が手錠の前に両手を突き出しているような構図だ。
たまらず真澄が失笑する。
マヤはと言えば、言われたとおりにしたのに何が可笑しいのだ、と言わんばかりに、鼻をへこませた。
その様子がまた可愛らしくて可笑しいのだが、真澄はマヤの機嫌を損ねぬよう、必死で笑いを噛み殺し、
「俺の説明不足だった。こっちだけでいいんだよ」
と、マヤの左手を掴むと、マヤの指の間に自らの長い指を滑り込ませた。
愛しむように、マヤの指をゆっくりとなぞっては優しく絡ませ、それをほどいては、また指をなぞって絡ませる。
マヤは困惑しながらも、真澄に言われたとおりに、目を瞑ったまま、彼の為すがままに任せていた。
実のところ、それは真澄の言いつけを守ってのことではなく、マヤは単に気恥ずかしくて、目を開けて彼を見ることができなかったのだ。
ただ指をなぞられているだけだというのに、まるで、彼と口付けを交わしているときに感じるような、甘く痺れた感覚がマヤの身体を
満たしていき、早く指を解放してほしいような、でももっと触っていてほしいような……そんな妙な心地にさせられて。
「まだ目を開けるなよ」
真澄がマヤの指を弄ぶことを止めてそう言いおいた直後、彼女の指先にひんやりとしたものが触れた。
「それ」がマヤの指先をくぐった瞬間、彼女がはっと息を呑む。
事前に真澄に釘を刺されていなければ、マヤは反射的に目を開けてしまっていたかもしれない。
それは、マヤの指先から指の付け根を目指して、ゆっくりと真澄によって押し進められていく。
実際にはほんの数秒にすぎないその時間がマヤにはひどく長く感じられ、トクントクン…と心臓の脈打つ音が、彼女の耳にやけに大きく
響いていた。
そして、それがようやくゴールに辿りつく。
「目を開けてごらん」
優しく促され、マヤが睫毛を震わせながらゆっくりと瞼をひらいた。
明順応で一瞬目が眩むが、次第に物体を正しく認知できるようになっていく。
まず目にしたのは、正面にある真澄の顔。
溢れんばかりの愛情で全てを包み込んでくれるような、そんな優しい瞳で、真澄はマヤを促した。――見てごらん、と。
マヤは、恐る恐る、左手を目の前にかざす。
ドクン――。
一際大きく、マヤの心臓が脈打った。
華奢な薬指にぴったりと収まっていたのは、小さなダイヤモンドの指輪。
小振りでシンプルなデザインでありながら、たしかな存在感と眩いばかりの輝きを放っている。
これが意味することは一つだ。
いくら鈍感なマヤだって、分からないはずがない。
それなのに、マヤは尋ねてしまうのだ。
これは夢じゃないのか、自分は都合のいい夢を見ているだけじゃないのか、と疑わずにいられないから。
「速水さん。これ…、これって……」
「手錠代わりだ。ちょっと目を離したら、君は今夜のように、すぐにどこかに行ってしまうだろう?だから、君がどこにも逃げられないように、
これで拘束しておこうと思ってな」
マヤが桜色に頬を染めると、柄にもなくキザなセリフだという自覚があるのか、真澄も照れくさそうに口元を歪めた。
だが、次の瞬間には一転、少し強張った面持ちで、真摯に、その言葉を放つ。
「俺と結婚してほしい」
マヤは目を瞠った。
全身が固まってしまったまま、真澄から目をそらせない。
「今夜、君にプロポーズするつもりだったんだ。ずいぶん時間がかかってしまったが、鷹通グループとの事業提携を白紙にして生じた
我が社の損失も、ようやく埋め合わせることができたし、それに、君と付き合いだしてもうすぐ一年だ。もうそろそろ、俺たちの関係を
公にしても問題はないはずだからな」
「ちょ、ちょっと待って。じゃあ、どうして今夜、あんなに怖い顔をしてたの? とてもじゃないけど、プロポーズする雰囲気には見えなかったわ」
「……君は、俺が緊張していたとは考えられないのか?」
「緊張…って。速水さんが?」
「俺だって人間だぞ。一生に一度の大舞台には、人並みに緊張くらいするさ」
真澄にしては珍しい、少し拗ねたような物言いだった。
それが、彼の照れ隠しのようで、マヤは言葉を失った。
「今だって、君の口から返事を聞けるまでは、落ち着かない」
普段はなにかにつけて余裕綽々な真澄が、恋人にたった一言を告げるのに、今夜、あれほどまでに硬い表情をしていたというのか。
そして、たった一言をなかなか言い出せずに、もどかしい思いをしていたというのか。
大会社の社長として、日々、自分の親ほどの年齢の重役たちを怒鳴りつけているあの真澄が、こんな小娘相手に、胸の早鐘を打たせて
いると?
そう考えると、マヤは、これまで張り詰めていた緊張感が急に身体から抜け落ちたように感じた。
今夜、ずいぶんと涙を流したはずなのに、またもマヤの涙腺が緩んでくる。
だが、それは、今夜流した涙の中で最も温かい、最上の涙だった。
「速水さんはずるい」
「ずるい?」
「だって、あたしの返事を聞く前に、指輪をはめちゃってるもの」
笑い泣きのマヤが真澄を非難するように言ってみたところで、そこには甘い響きだけが溢れている。
そんな空気に安堵したのか、先程の硬い表情はどこへやら、「それもそうだな」と途端に真澄も相好を崩した。
「何でもかんでも勝手に決めちゃうところが、強引で、いかにも速水さんらしいと思う」
「何事に対しても、先手必勝がモットーなんだ」
「そのわりに、恋愛には慎重なところもおありのようですが?」
痛いところを突かれて、真澄が一瞬、うぐ、と押し黙るが、次の瞬間には、参った、と言わんばかりに破顔した。
「自分のモットーを曲げてでも、大事にしたい人がいるからな。それとも、鈍感で、馬鹿で、おまけに普段は強引なくせに君に対してだけは
臆病になってしまう、そんな情けない男はいやか?」
可笑しそうに尋ねる真澄の胸に顔を埋めて、マヤは彼のシャツを小さく握り締めた。
「いやじゃない…。鈍感でも馬鹿でも、強引でも臆病でも、どんなあなたでも、好き。あなたが好き…、大好きよ……」
「俺と結婚してくれるな?」
「はい……」
「俺はこんな男だが、君を幸せにしたいという気持ちは誰にも負けない。一生君を愛して、守りぬくと誓うよ」
「……あたしを幸せにしてくれるのなら、速水さんも幸せになってくれないとだめなの。あたしもあなたを幸せにしたい。だから、二人一緒に
幸せになろうね」
マヤが細い涙を流しながら満面の笑みを浮かべると、真澄は彼女の左手を引き寄せて、愛しげに唇を押しあてた。
*このお話は地下へと続きます♪そういったお話が苦手な方は、ここで完結だと思ってくださいね〜*
 
|
