| 花咲く夜
〜written
by 真砂〜
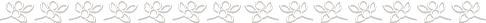
真澄への想いを込めて「紅天女」を演じたマヤと、マヤへの想いを貫いて、自分の気持ちに正直に生きたいと願った真澄。
二人の恋が成就したのは、今から一年近く前、「紅天女」の試演の直後だった。
『ずっと君が好きだった。誰よりも愛してる』
真澄が紫織との婚約を解消し、マヤに想いを伝えると、彼女はそれに応えた。
マヤもまた、苦しく切ない想いを抱き続けていたことを真澄に打ち明けて……。
だが、彼らの関係は表沙汰にされることはなかった。
時期と状況があまりにも悪すぎたのだ。
結婚を目前にしての、真澄と紫織の破談。
それと間髪を入れずに始まった、「紅天女」の上演権獲得に野心を抱き続けてきた男と「紅天女」の上演権を持つ女の交際。
これらは、たとえ、真実がどうであろうとも、口さがない者たちの好奇心を掻き立てる格好のネタになってしまうことが目に見えていた。
自分のことなら何を言われようとかまいはしない真澄であるが、この場合、よりダメージを受けるのは、女優として常に表舞台に
立っているマヤのほうである。
『時期が来るまでは、俺たちの関係は伏せておこう』
いわれなき憶測や心無い中傷からマヤを守るために、そして、傷つけてしまった紫織の気持ちを慮って、
「やましい付き合いをするわけでもないのに、すまない」 と詫びた上で、真澄から申し出たことだった。
マヤにも異存はなかった。
それがマヤのためを思っての提案だということを痛いほどに理解していたし、また、紫織に対する配慮がいかにも真澄らしく
誠実であると思えたからだ。
そうして二人の交際が始まったものの、多忙な二人が共に過ごせる時間は充分ではない。
ましてや、普通の恋人同士のように、おおっぴらに人目につく場所に行くこともできない。
だが、だからこそ、彼らは限られた時間をより大切にし、互いのことをより思いやり、幸福で充実した日々を送っていた。
しかし、それなりの時間が経過した頃、不意に、マヤの胸にある不安が生じた。
それは一見些細なことのようで、実は、二人にとって最も深刻かもしれないことだ。
一度生じてしまったその不安は消えることはなく、まるで半紙に墨汁が滴り落ちたかのように、マヤの心に黒い染みを作り、
じわじわと拡がっていった。
そして、ついに、マヤのその不安を決定付けるかのような一本の電話が入ったのだ。
『……大事な話があるんだ』
何かを思いつめたような硬い声。
電話を通して、真澄の張り詰めた空気がマヤに伝わってくる。
来るべき時が…来た?
直感的に、マヤはそう思った。
胃が締め付けられるように痛み、背中にじっとりと冷たい汗を感じる。
からからに干乾びてしまいそうになる喉の奥から、マヤはどうにか声を搾り出した。
「大事な話…って……?」
『それは……。電話で話すべきことじゃない。すまないが、明日の夜、時間を作ってくれないか?』
そこには有無を言わせぬ響きがあった。
あるレストランに、特別室を借りきっていると真澄は言う。
そこで、マヤに大切な話をしたいのだ、と。
幸福な夢から覚める時がついにやって来たのだ、とマヤは確信した。
こんな日が来ることを少し前から覚悟していたはずなのに、受けた衝撃はやはり大きい。
一瞬にして、体中の血液が凍り付いてしまった気がした。
心が千々に乱れ、気を抜けば、そのまま床にへたり込んでしまいそうなほどだ。
だが、マヤは壁に身体を預け、必死で足を踏ん張った。
自分は分不相応な恋をして、それが叶って、真澄にずっと大切にしてもらって、幸せだった。
だから、これ以上真澄に無理をさせて、自分に縛り付けるようなことはしてはいけない。
どんなに苦しくても、悲しくても、明日は笑ってさよならを言うべきなのだ。
真澄に負担をかけないように――、その一心で、マヤは己を奮い立たせた。
「分かりました。じゃあ、明日の夜、7時に……」
声が震えてしまわないように、腹筋と喉になけなしの力を込めて、マヤは電話を切った。
身を切られるような痛みと底の見えない悲しみを感じながら――。
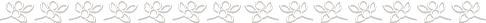
すでに数十分以上、バッグの中で携帯電話が鳴り続いている。
マヤは部屋の隅で膝を抱えたまま、ぼんやりとその音を聞いていた。
誰がかけてきているのか、携帯のディスプレイを見るまでもない。
それが分かっているからこそ、罪悪感を覚えながらも、あえて電話を無視し続ける。
いつもなら、彼専用のこの着信音が流れ出すとワンコールで反応してしまうほどなのに、
今はそれがまるで物悲しい映画のエンディング曲のように聞こえて、マヤを息苦しくさせていた。
いっそのこと、消音にするか電源をオフにしてしまえばいいのに、そう踏ん切りをつけることのできない中途半端な自分を、マヤは
情けなく思う。
この音は、マヤにとっては、二人を繋ぐ最後の糸も同然だった。
電話に応答しようとそうでなかろうと、辿りつく結果は同じだというのに、この呼出音が続く限りは真澄の心の中にまだマヤが
存在しているのだと思うと、このままずっとこの電子音を聞いていたい気さえする。
自分は今、何をしているのだろう。
なんてことをしてしまったのだろう、とマヤはただ呆れるばかりだ。
真澄がこんな自分を見限りたくなっても当然だと思う。
真澄に笑ってさよならを告げるどころか、マヤは「大事な話」とやらを聞くのが怖くて、話を切り出される前に、こともあろうに
彼に黙ってレストランから逃げ出してしまったのだ。
今夜の真澄は、硬く強張った面持ちを崩さず、口数も少なかった。
二人が付き合い始めてからそんな様子の真澄は初めてで、彼が言いにくい話を抱え込んでいるのは一目瞭然だった。
張りつめた空気は伝染し、明るく振舞おうと心に決めていたマヤの口数も、自然と減ってしまっていた。
もっとも、鉛のように重い足を引きずって真澄との夕食に臨んだマヤは、前向きな決意に反して心の中は淀みきっており、
饒舌になりようがなかったのだが。
そうして、会話が弾まないまま最後の晩餐は進み、締めくくりであるデザートが運ばれてきたときに、ついにマヤの緊張が
極限に達してしまった。
デザートが終わってしまえば、あとは真澄に引導を渡されて、それでお終いだ。
物分りの良い大人の女を演じて真澄を解放してあげよう、と腹をくくっていたつもりだったのに、土壇場にきて、マヤの正直な心が
悲痛な叫びをあげ続けるのだ。
真澄と離れたくない。別れの言葉など聞きたくない。そんなことは耐えきれない、と。
だから、マヤは化粧室に行くとだけ告げて席を立った。こんな気持ちを抱えたまま真澄のそばにいるのは、針のむしろだったからだ。
そして、気付けば、そのままレストランを飛び出して、自宅マンションへと踵を返していたのだ。
レストランを出てすぐに拾ったタクシーの中で携帯が鳴り始め、応答することも切ってしまうこともできないまま、現在に至っている。
黙って姿を消してしまったマヤを、真澄はきっと心配しているだろう。
ましてや、携帯もいっこうに繋がらないとくれば、なおさらだ。
そこで、ふとマヤの思考が止まった。
もしかしたら、真澄はいい口実ができたと喜んでいるかもしれない。
レストランではなかなか話を切り出せない様子の彼だったが、マヤがこんな非常識なことをしでかしてしまった今なら、
何のためらいもなく、マヤに死刑宣告をすることができるのかもしれない。
そんなことなら……真澄に呆れられて終わりを迎えるくらいなら、彼から逃げ出さず、当初の予定通り、無理をしてでも笑って
別れたほうがやはりマシだったかもしれない。
だが、今さら後悔したところで後の祭りだ、とマヤが大粒の涙を浮かべたときだった。絶え間なく鳴り響いていた携帯の音が
ぴたりと止み、今度は部屋の電話がけたたましく鳴り始めたのは。
数回の呼出音の後、ピーという発信音に続いて、普段は冷静沈着を絵に描いたような男の、ひどく取り乱した声が流れてくる。
『マヤ! 帰っているのか!? いるのなら、頼むから電話に出てくれ!』
マヤは目を瞠った。
今、最も聞きたくなくて、最も聞きたかった、最愛の人の声だった。
その声から、真澄がどれだけマヤを心配しているのかが、直接心に染み入るように伝わってくる。
言いようのない罪悪感と自己嫌悪で、マヤは胸を押し潰されそうな心地になった。
『どうして携帯にも出ないんだ? 俺と話したくないのか……?』
苦しげに訴えかける真澄の言葉が棘となって、マヤに鋭く突き刺さる。
マヤは眉を寄せ、唇を噛み締めた。
『……このメッセージを聞いたら、絶対に俺に連絡を入れろ。いいな』
明らかに苛立ちと怒りを押し殺した声で、メッセージの録音が終了した。
その後、マヤがどれだけ部屋の電話機と携帯を見守り続けても、それらはもうけたたましく自己主張することはなく、
沈黙を守り続けた。
きっと、真澄は呆れ返ってしまったのだろう。
マヤから連絡を入れない限り、真澄はもう彼女と接触をとる気はないに違いない。
とうとう真澄との最後の糸も切れてしまったのだ、とマヤは思った。
糸の切れた凧のように、真澄はマヤの手の届かないところへ遠ざかってしまったのだ、と。
マヤは空虚な心で、膝を抱えたまま、嗚咽し続けた。
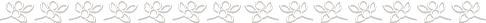
玄関のチャイムが鳴った。
マヤは雷に打たれたようにその音に反応し、気付いたときには玄関でドアノブに手を伸ばしかけていた。
もしも真澄だったら、という期待ばかりが先走っていた自分に気付き、マヤは皮肉げに唇を歪めた。
期待してどうするのだ。
もし真澄だとしても、マヤが楽しくなるような話をしに来るはずはないというのに。
もはや、あわす顔などないというのに。
マヤがドアの前で身構え、息を潜めていると、ドアをどんどんと叩く音と、聞き慣れた女性の声が聞こえてきた。
「マヤー? いるんだろ? あたしだよ、開けて。あんたの留守中に荷物預かってるんだけど」
麗だ。
マヤはほっと息をついた。
麗とマヤは、白百合荘を出た後に同じマンションの隣同士で部屋を借りており、相変わらずの付き合いを続けている。
この階にはマヤと麗の二部屋だけで、互いの留守中に配達された荷物などを預かることはよくあることだった。
「ごめん、ちょっと待って。今開けるね」
マヤは慌てて涙を拭い、ぎこちないながらも笑顔を取り繕った。
そして、なんのためらいもなく鍵を外し、ノブを回すと、その瞬間、わずかに開いたドアの隙間に勢いよく男の靴が滑り込んでくる。
驚き、咄嗟にマヤがドアを閉めようとしても、一歩遅かった。
開きかけたドアを男の手が掴み、マヤがそれを閉じようとするのをものともせずに、やすやすとドアは押しひらかれてしまった。
マヤは慌ててリビングへと逃げ込むが、無作法に部屋に上がりこんできた侵入者に腕を掴まれ、乱暴に引き寄せられる。
そのとき、マヤは鋭く尖った真澄の視線にぶつかり、本能的な怯えを感じて身を縮めた。
――ぶたれる!?
マヤが目を閉じて歯を食いしばる。
だが、マヤが感じたのは、頬を張られる痛みではなかった。
痛みは痛みでも、身体が折れてしまいそうなほど強く抱きしめられている、その痛みだ。
そして、密着した身体から、真澄の鼓動と、かすかな煙草の匂いが伝わってくる。
それが心地よくて、凝り固まった肩の力が自然と抜けていくのを、マヤは感じていた。
思えば、おかしな話だった。
もともとマヤは煙草が苦手なはずなのに、真澄の身体に染み付いた煙草の匂いにだけは、安らぎのようなものを感じてしまう。
マヤにとっては、真澄の全てが特別なのだ、と彼女は改めて思い知らされるのだ。
「良かった、君が無事で……」
震えて今にも泣き出しそうな声に、マヤの息が止まりそうになった。
ぐったりと倒れこむようにして、真澄の額がマヤの肩に押しあてられた。

イラスト:桜屋 響さま
「この馬鹿…。本当に心配したんだぞ。黙っていなくなった上に携帯にも出ないし。店員から、君が一人で店を出てタクシーに
乗り込むところを見たと聞かされても、まさか誘拐されたんじゃないのか、事故に遭ったんじゃないのかと不吉な想像ばかりが
膨らんで、生きた心地がしなかったんだぞ。君は俺の心臓を止めたかったのか……!?」
心底苦しげに真澄が唸る。
マヤがこれほど取り乱した真澄を見るのは初めてのことだ。
マヤを案じる深い思いが、真澄の全身から迸っていた。
マヤは自分のとってしまった行動を、今さらながら、心底恥じ入っていた。
どんな理由があろうとも、真澄をここまで心配させてしまったのは、罪だ。
「ごめんなさい……!」
それは、マヤの口をついて出てきた、真摯な謝罪の言葉だった。
それが真澄にも伝わって、彼はそれまでの硬い表情を少しだけ和らげた。
「具合が悪かったわけじゃないんだな?」
マヤが小さく頷くと、真澄が安堵の息を吐いた。
「そうか…。良かった……」
「あ…、あの」
「ん?」
「怒ってないの……?」
「そりゃあ、怒ってないわけがないだろう?」
素直に肩を震わせるマヤを見て、真澄が自嘲気味に言葉を継いだ。
「だけど、こんな真っ赤な目を見せられて、俺が君を怒ることができると思うのか? 俺を思って泣いていたんだろう?」
マヤが目を瞠ると、真澄はさらに皮肉っぽく苦笑した。
「でも、反則だぞ。君の涙に俺がどれだけ弱いか知っているくせに」
真澄がマヤを優しく抱きなおすと、マヤはごめんなさい、と再び呟いて、彼の胸に顔を埋めた。
すると、咳払いが一つ、彼らの後ろから降りかかる。
「……えーと。恋人のいない身としては、目のやり場に困ると言うか、当てられちゃうんですよね。そういう抱擁シーンは」
リビングの入り口で、居心地悪そうに目を泳がせているのは麗だ。
マヤが赤くなって真澄から一歩下がると、麗がマヤの近くまで歩み寄ってきた。
「マヤが帰ってきてないかって、速水社長から電話をもらってね。うちのベランダからあんたの部屋の灯りが確認できたから、
速水社長に協力させてもらったんだよ」
麗は、やれやれ、といった顔をして、マヤの額を小突いた。
「何があったかは知らないけど、こういうのはマヤらしくないな。いつでも直球勝負があんたの売りだったはずだろ?」
「麗……」
「あんた宛の荷物はたしかに届けたからね。ちゃんと話し合って、仲直りするんだよ」
マヤの頭を撫でてから、麗は真澄に悪戯っぽい視線を投げかける。
「じゃあ、私はこれで。今夜は『つきかげ』のメンバーのところにでも泊まりますから、大声を出しても大丈夫ですよ。
痴話喧嘩をなさるなり、熱い抱擁の続きをなさるなり、ご存分に」
「面倒をかけてすまなかったね。天の岩戸から天女様をおびき出すことができたのは、君のおかげだ。ありがとう」
「いえ、とんでもない。速水社長にご面倒をおかけしているのは、うちの妹分のほうですから。でも、この子は理由もなく人に
迷惑をかけたりするような子じゃないんです。だから、どうか最後まで話を聞いてやってください。……お願いします」
「ああ、分かってるよ」
麗も真澄も、それ以上の言葉は必要なかった。
マヤが演劇を志したときから彼女をずっと支え続けてきた麗と真澄は、マヤにとっての親友と恋人とそれぞれ立場は違えども、
同じ者を同じように慈しむ者同士、共感し、互いに全幅の信頼を置いている。
穏やかに微笑む真澄に麗もまた穏やかな笑みを返し、会釈をしてその場を後にした。
 
|
